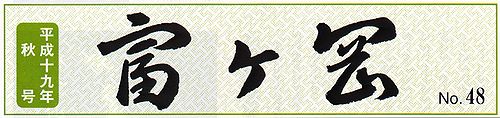

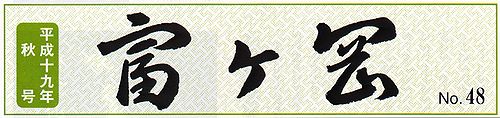

|
石造燈籠 伊奈忠宥奉納一対 |
| 正面の大鳥居をくぐり右手にある大関碑と昭和天皇御製碑の間にひっそりと一対の石燈籠が立っています。 これは宝暦八年(1758)3月15日に関東郡代・伊奈忠宥により奉納されたもので、左右ともに261cmの高さの安山岩でできており、刻名は左右同じで次のように刻まれています。 |
|
奉寄進 石燈籠兩基 |
| 関東郡代 伊奈氏 伊奈氏はもともと信州伊奈郡の出自であると伝えられ、徳川家康の父、松平広忠の頃より仕える三河譜代の家系です。 関東郡代は江戸時代に西国・美濃・飛騨とともに設置された郡代の一つで、関八州の幕府直轄領を司る地方官です。本来、郡代は代官とともに勘定奉行の支配下でしたが伊奈氏は勘定吟味役・勘定奉行職を兼ねることもありましたので、老中支配下となりました。 初代郡代伊奈半十郎忠次は家康に仕え、小田原征伐や朝鮮出兵の兵糧輸送・街道整備を担い、江戸移封の際に従五位下備前守に任じられ、関東代官頭として大久保長安・彦坂元正・長谷川長綱とともに関東支配の行政を司り、主に関東を中心に各地で検地、新田開発、河川改修、また、中山道などの宿駅の整備を行い江戸幕府の財政基盤の確立に寄与しました。 そして三代忠治より職名が関東郡代となり十二代忠尊が改易されるまで、その職を受け継ぎ、その功績によって同族の忠光盈が名跡を継ぎ旗本として幕末まで続きました。 この石燈籠を奉納した忠宥は十代目であり明和元年(1764)より起った武蔵・上野・下野の一揆(中山道伝馬騒動)を鎮める功績を残しました。 |